
唐突ですが、ゲーム界の生ける伝説、見城こうじさんについてベーマガの歴史という視点から書きたいと思います。
以下の内容は、手元にあるベーマガとネットの情報をまとめただけです。特別な情報は一切ありません。
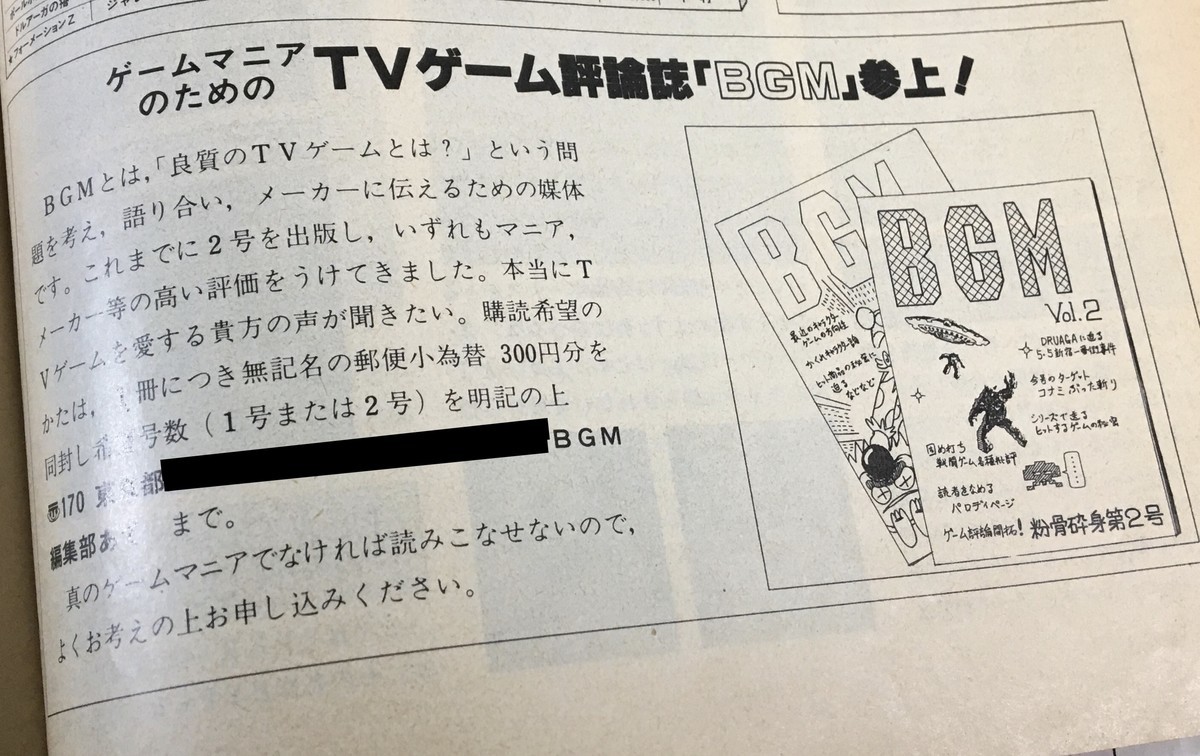
見城さんの出発点は「BGM」という同人誌。作ったのは見城さんと手塚一郎さんです。
1984年9月号のスーパーソフトマガジン(ベーマガの付録)に「BGM」のお知らせが載っています。BGMは何の略か、38年間謎のままです。読んだことないので何とも言えませんが、「TVゲーム評論」ってのが当時としては、全く未踏の領域です。
見城さん達はBGMをベーマガ編集部に売り込んだのを機に、ライターとして活躍するようになります。
1984年12月号のスーパーソフトマガジンの「第22回アミューズメントマシンショー速報!」の中にBGMの記述があります。
本誌でもおなじみのBGMやEXCHANGERらプレイヤーの協力をえて取材してきました。
見城さんはベーマガ1986年8月号から「VIDEO GAME GRAFFITI(ビデオゲーム・グラフィティ、略してVGG)」を連載開始。「ナムコ・ビデオゲーム・グラフィティ」と同じ名前を使ってしまうとは、、、。
ベーマガ1986年11月号ではVGG内に次のコメントが。
実は今、ベーマガの編集部でゲームの歴史をまとめた本を作ろうという一大プロジェクトが提案されているのです。今までにない大きな企画なのでかなり難航しています。
VGGは各地のゲーセンのゲームを列挙するだけという、恐ろしく地味なコーナーでした。しかし、ここに来て「ゲームの歴史」という方向性が加わります。1987年4月号からVGGの一部を使い「ビデオゲーム史講座」を開始。この「隙があったらゲームの歴史を勝手に語り出す」という性分は、「ビデオゲームCLASSIC GUIDE」でも発揮されます。
そして、このコーナーは「アルカノイドは名作じゃない」的な発言を載せ、物議をかもします。ベーマガ1987年6月号での見城さんのコメントは次の通り。
たとえば『アルカノイド』は大ヒット作だし僕も好きなゲームだけど、だからと言って「名作」なんて言葉はまったく当てはまらないということだ。
これに対しての読者の反論は1987年11月号まで続きました。見城さんはリメイクものに対しては厳しい評価を下していました。逆にアイデア重視の作品は高評価。そんな見城さんがゼビウスをリメイクしているのが、面白いところ。
その後、ベーマガ1988年4月号には、創刊70号記念特別企画としてVGGスペシャル版がカラーで掲載されます。本文中には次の記述が。
VGG別冊「VIDEO GAME HISTORY」が、ただ今企画進行中です。
これは約一年半前にアナウンスされた「ゲームの歴史をまとめた本」のことでしょうか? 実は企画が死んでなかった。
見城さんのベーマガでの活躍は1990年まで続きます。1990年5月号で「CHALLENGE! HIGH SCORE!」の担当を終了。1990年6月号で「見城こうじの激論!ビデオゲーム」終了。突然、誌面から姿を消してしまいます。理由はナムコに入社したためだったわけですが、当時の読者は知る由もありませんでした。

上の写真は1990年10月号掲載のCHALLENGE! HIGH SCORE!。この号だけは異例で、エッセイ風の記事が1ページ追加されました。これを書いたのは一緒にチャレハイを担当していた、やんまさんです。「ゲームの歴史をまとめた本」が最初にアナウンスされてから4年近くが経過していますが、まだ企画が死んでいませんでした。
それから数年が過ぎて、ベーマガ1992年5月号で「コズモギャング・ザ・ビデオ」の記事が掲載されたのですが、本文の最後に次の記述が。
でも、なんでこんなに凝っているかって? それはエンディングのスタッフ・クレジットを見れば……そう、ゲーム・デザインがあの見城こうじ先生なんだもの。
これを書いたのも、やんまさんです。
そして、ベーマガ1993年1月号の「コズモギャング・ザ・パズル」の見出しが次の通り。
見城こうじ氏が放つ「落ちもの」最新作
これを書いたのも、やんまさんです。
この後、やんまさんはベーマガを卒業して、1994年にセガに入社。1999年には「電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム ドリームキャスト版」でディレクターに就任します。見城さんの「カスタムロボ」に対して、やんまさんは「バーチャロン」という、この関係性が面白いです。
参考 開発者インタビュー「Creators Note」 #14 山下 信行
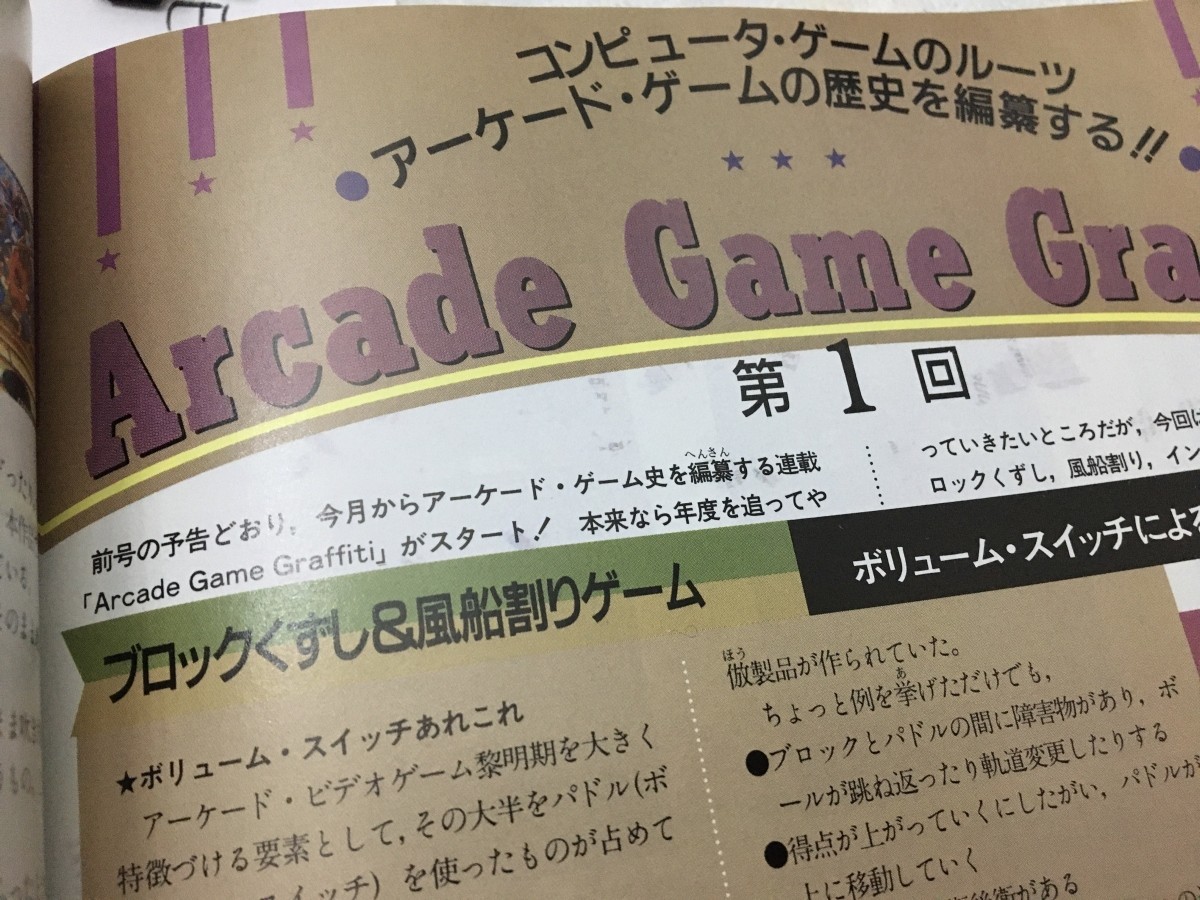
ベーマガ1994年2月号から「Arcade Game Graffiti(アーケード・ゲーム・グラフィティ)」が連載開始。「ゲームの歴史をまとめた本」のアナウンスから既に7年以上が経過してますが、そのコンセプトを受け継いものだと感じます。これ、著者名が書かれていないのですが、見城さんが書かれているんじゃないか?と思いますが、間違っていたらごめんなさい。ベーマガを卒業したかに思えて、実は卒業していなかった? このへんの情報がさっぱりなので、いつかどこかでカミングアウトして頂きたいです。
Arcade Game Graffitiの連載は5年続きました。ぜひ、まとめて読みたいです。
最後に掲載されたのが、ベーマガ1999年2月号。この時点で「1985年」編の第12回目でした。1年ぶんのゲームを紹介するのに1年を費やす。これだと永久に現在に追いつかないのでは。
結局、1986年以降の歴史が語られないまま連載が終わってしまいました。

ベーマガ1995年12月号にはアーケード版の「ゼビウス・アレンジメント(1995年)」が掲載されています。伝統の全マップ掲載。スタッフクレジットによると、「ゲーム・アレンジメント」という役職の2名のうち一人が見城さんでした。
上の写真はPS3で配信してるプレステ版「ゼビウス3D/G+」。この中に「ゼビウス・アレンジメント」が収録されています。
ナムコを退社後、見城さんは1996年にノイズを設立。
ベーマガ1999年2月号(200号記念)には見城さんの近況としてNINTENDO64用ゲームを開発中であると書かれていますが、これが「カスタムロボ」だと思います。
ネットで読める見城さんの発言・記事の数々はこちら。
・2001年 ノイズ公式サイトのコラム(現在は読めません)
・2005年 ノイズ公式サイトのblog (現在は読めません)
・2013年 twitter
・2016年 ゲーム文化保存研究所
・2017年 note「アはアーケードのア」
私はtwitterはノーチェックですが、もしかして、重要な情報が眠っているかもしれません。
ノイズで掲載していたコラムはアーカイブで読むことができます。
参考 連載コラム
これによると、カスタムロボ開発の経緯が細かく書かれています。個人的に面白かったのは、最初に作っていたゲームをボツにしたという話と、サイバリオンの作曲者さんにサイバリオンっぽい曲をオーダーしたという話です。
ゲームデザイナーとしての見城さんについては、ベーマガの範囲外なので、どなたか詳しい方に書いて頂きたいです。